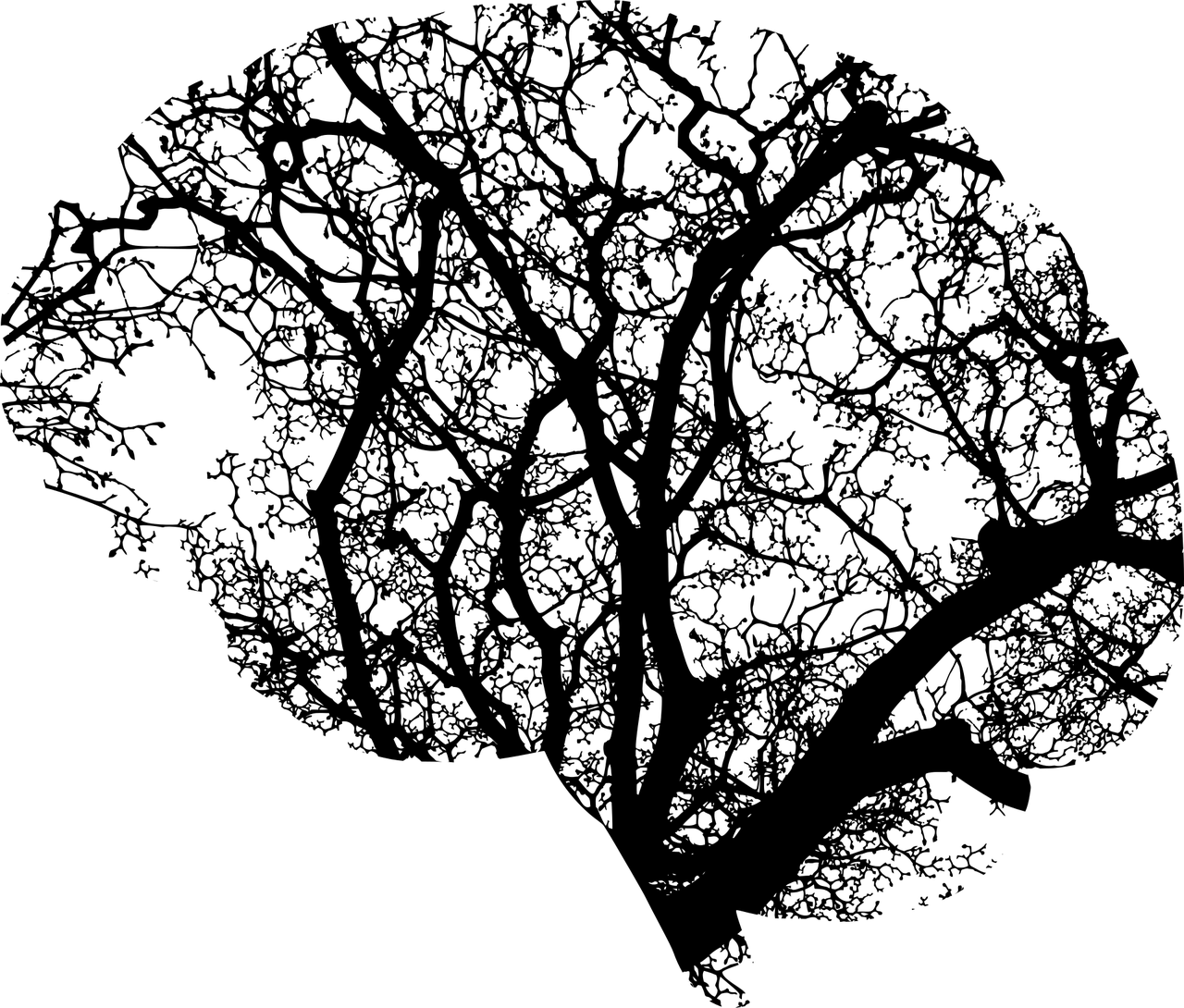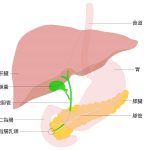がんではない慢性痛は脳の変化から来ている
慢性の痛みは急性の痛みと異なり、脳の変化が痛みを増幅させたりしていることがわかってきています。
医学書院が出している週刊医学界新聞の平成31年12月3日号に、半場道子先生の『慢性痛への挑戦』という記事が掲載されました。
語弊を承知で言えば、がんの慢性痛は比較的わかりやすいです。
それらの疼痛は、画像検査で原因を特定できるからです。
しかし、がん「ではない」病気(非がん)の慢性痛は容易ではありません。
慢性腰痛や線維筋痛症のように、画像で原因が特定できないものがあるからです。
かといって近年の理解では、「痛みはない」「気のせい」とはなりません。
心因性疼痛と呼ばれてきたそれは、「心」というよりも、脳の変化であることが指摘されてきています。
『慢性痛への挑戦』では、その痛みを端的に解説する内容でした。
『慢性痛への挑戦』から、興味深い部分を紹介
このような器質的な要素を欠く痛みは、脳内の「快の情動系」の機能低下と、痛みを和らげる神経系の「下行性疼痛抑制系」の同じく機能低下に生じているのだそうです。先述の記事では「扁桃体(へんとうたい)」の関与も示唆されています。
そして痛みが、不安や絶望に関与し、孤立感や恐怖感につながり、意欲や食欲も低下します。
他に、高齢者の慢性疼痛にも言及されています。
例えば変形性関節症では、座り過ぎが筋萎縮となり、筋のサポートが減るぶん関節に負担がかかって関節軟骨が摩耗してゆくことが終わりなき衰弱と疼痛のスパイラルを招きます。
そこで筋肉を鍛え、筋量を増やすことが対策となります。
痛みの成り立ちによっても対処法が変わるのです。
非器質性の痛みの治療とは?
―慢性痛治療のポイントは何ですか?
まず大切なのは、急性痛の段階でできるだけ早期に痛みを遮断することです。痛みは火事に似ています。痛みのシグナルは上位脳回路網に変化を起こし慢性痛に転化し、より対処が難しくなってしまうからです。神経障害性の痛みは特に脳への影響が大きいので、抗けいれん薬などを使って、早期に痛みを遮断する必要があります。
―非器質性の慢性痛に転化した場合は、どのような治療を効果的ですか。
抗うつ薬などの薬物療法、筋運動、認知行動療法やマインドフルネスなどが挙げられます。
(中略)
―慢性痛患者に向き合う医療者が心掛けるべきことは何でしょう。
(中略)
慢性痛治療にはNarrative-based Medicineが役立ちます。痛みの症状、生育歴、生活パターンなどを問診する間に痛み軽減のヒントが得られることは多いです。また、痛みを完全になくすことは望めなくても、痛みが軽減すれば一歩前進と受け入れ、生活を楽しむよう助言することも効果的です。医師に抱く信頼感が大きいほど、助言を通じて痛みの軽減に結び付くように思います。
痛みが続くことが脳の変化を招き、難治性になる。
これは専門家には常識ですが、知られていない情報です。
痛みを、痛み止めを使わないで放置することが、慢性化の一因となるのです。
結構多い術後遷延性疼痛
手術後に痛みが慢性化する、術後遷延性疼痛。
「CPSP(術後遷延性疼痛) は術後患者の約10〜20%に発症し、約1%で治療抵抗性である。⼤規模な観察研究において、術後1年の時点で2.2%の患者が重度のCPSP(0〜10 の数的評価尺度で6以上)を訴えたことが報告されている」とされます。
術後遷延性疼痛(Chronic postsurgical pain: CPSP)
どれくらいの時期続けば慢性痛と捉えるのかについては「術後少なくとも3か⽉間持続する疼痛(定義により2〜6か⽉とするものもある)」となっています。
手術の成功・不成功にかかわらず、なります。
しかし、一部の手術医師はこの診断を厭うようで、診断が付けられずに長期放置され、慢性痛が増悪しているケースが散見されます。
この診断が付いたからといって、手術が下手や失敗ということではありません。
前向き観察研究によるリスク因⼦の分析によって5つの重要な予測因⼦が特定されています。
①感情的過負荷/過剰ストレス
②⼿術部位の術前からの疼痛
③術前からの他の慢性疼痛の存在(例:頭痛)
④急性術後痛
⑤振戦、不安や睡眠障害のような併存ストレス症状
すなわち、術を受ける側の要素が関係しています。
ところが、一部術者は責められているように感じ、この急性痛及び慢性痛を放置しがちです。
また画像検査では所見が出ないことが多いので、そこから「気のせい」や「痛みを感じやすい人」等のレッテルが貼られてしまっていることもあります。
重要なことは早期に痛みを抑え込むこと、慢性化した場合は適切に診断し治療することです。
しかししばしば放置され、慢性痛へ発展しているケースがあります。
ただそのようなケースでも、鎮痛薬療法で一度痛みを抑え込むと、痛みが減って鎮痛薬が最終的には中断可能な例も散見されます。
なおがんの痛みの場合と、術後痛も含めたがんではない慢性痛の場合は、治療や考え方が多少以上異なるので、痛み全般への十分な理解が必要であり、慢性痛の専門家や、緩和ケア医の中でも慢性痛の治療に精通している医師の診断・治療を求めるのが良いでしょう。