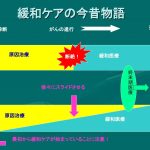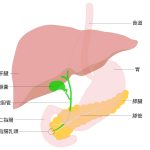「緩和ケア」という言葉が出た瞬間、心が凍る理由
診察室で主治医がこう言う。
「緩和ケアも考えていきましょう」
その瞬間、
胸がざわつき、頭が真っ白になる。
「もう終わりなのか」
「見放されたのか」
「余命が近いのか」
――怖くなるのは、決しておかしなことではありません。
なぜ「緩和ケア」は怖く聞こえるのか
日本では長い間、
- 緩和ケア=終末期
- 緩和ケア=もう治療できない
- 緩和ケア=あきらめ
というイメージが広がってきました。
そのため、
医師がその言葉を口にした瞬間、
“線を引かれた感覚”を持つ方が少なくありません。
けれど、それは緩和ケアの本質とは違います。
本当は、何を意味しているのか
しばしばあるのが、主治医が言いたかったのは、
- 痛みや不安を専門家にも相談できる
- 治療と並行してサポートを受けられる
- 一人で抱え込まなくてよい
という提案です。
つまり、
治療をやめる宣言ではなく、支えを増やす提案であることが実は少なくないのです。
「怖い」と感じるあなたは正常です
外来でよく聞く言葉があります。
「緩和ケアと言われたとき、もうダメだと思いました」
でも実際には、
- 治療は続いている
- 生活も続いている
- 時間も流れている
緩和ケアが始まったからといって、
人生が終わるわけではありません。
怖くなるのは、
緩和ケアが怖いのではなく、先が見えないことが怖いのです。
緩和ケアは“最期の医療”ではありません
緩和ケアは、
- 痛み
- 息苦しさ
- 不安
- 眠れない
- 家族とのすれ違い
こうした“つらさ”を扱う医療です。
それは病気の早い段階から使うことができます。
緩和ケアは、
終わりの医療ではなく、支える医療です。
もし今、怖いなら
もしあなたが今、
「緩和ケア」と言われて怖いと感じているなら、
それは弱さではありません。
その不安をそのまま、医師に伝えてよいのです。
「緩和ケアと言われて、怖くなりました」と。
そこから対話は始まります。
まとめ
「緩和ケアを言い出されるのが怖い」
その感情の裏には、
- 情報の不足
- 言葉の誤解
- 未来への不安
があります。
緩和ケアは、あきらめではありません。
怖いと感じたその瞬間こそ、支えが必要なタイミングなのです。